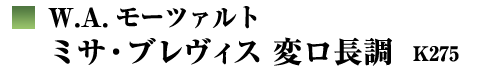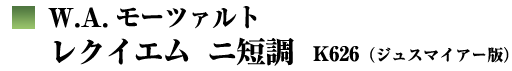![]()
― 定期演奏会の記録 ―
![]()
プログラム・曲目紹介
![]()
- キリエ
- グローリア
- クレード
- サンクトゥス
- ベネディクトゥス
- アニュス・デイ
![]()
- レクイエム
- ディエス・イレ
- トゥーバ・ミールム
- レックス・トレメンダエ
- レコルダーレ
- コンフターティス
- ラクリモサ
- ドミネ・イ工ズ
- ホスティアス
- サンクトゥス
- ベネディクトゥス
- アニュス・デイ
![]()
楽曲解説 ミサ・ブレヴィス 変ロ長調 KV275
モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart.1756〜1791)のミサ曲といえば、「載冠ミサ」や「ハ短調ミサ」のように、ご存知の通りの大曲ばかりが目立つが、数の上では今回取り上げる曲のような「Missa brevis ミサ・ブレヴィス」の形態が多い。「brevis」とは「短い、小さい」という意味で、この曲群は特別でない普段の日曜に行われる「略式ミサ」に使われた。彼の生きたザルツブルグでは、もっぱらこの種のミサ曲を重宝がる傾向にあった。また当時の大司教はミサ自体を45分以上になってはならない、という制限を設けたので、宮廷音楽家のモーツァルトは、テキストの省略、フーガの簡略化など、切り詰めた内容での音楽づくりにより、20分前後で終わるミサ曲を提供してゆかねばならなかった。
「ミサ・ブレヴィス 変ロ長調 KV275」もこの背景により成立したものであるが、この曲の特色は他のブレヴィス曲に比べて、独唱の活躍の場が多いのと、旋律にかなり世俗色、抒情性が強いことである。とくに独唱部に対してはそれが顕著で、初演の際カストラート歌手チェッカレッリが見事な歌唱を聴かせたという。冒頭のKyrie(求憐誦)からそうであるように、独唱が合唱を先導する形を多くとる。オーケストラは控え目な伴秦に始まり、声楽に支配されているが、Credo(信仰宣言)に対しては決してそうでなく、声楽の和声的な旋律に対して華やかで装飾にあふれたオブリガードを奏することにより、主題の方向づけを作用させる働きを強く持つ。この書法はSanctus(聖なるかな)にも用いられ、しつこさを与えることなく後に続く声楽フーガにつないでいる。終楽章のDona nobis(平安を与えたまえ)では独唱と合唱が、短い俗謡風の旋律を交互に延々と歌いつなぐ。この形式は、後のオペラ「後宮からの誘拐 KV384」のフィナーレにも用いられる。
楽器編成は、ヴァイオリン2部、低音部楽器、オルガン、任意によるトロンボーン3部(本日の演奏には用いない)だけの極めて小編成で成り立っている。
楽曲解説 レクイエム ニ短調 KV626
モーツァルト最後の作品であり、死の前日まで筆が進められたか、ついに未完に終わった。まさに自分の死のためのレクイエムとなったこの曲にかける彼の情熱は、円熟した書法の境地を行くこの音楽の比類なき美しさに表れている。聴く者、演ずる者に深い感動を与える類まれなこの音楽を彼がすべて完成出来なかったのは、非常に残念なことである。
モーツァルトの真筆である部分は、Introitus(入祭文)の全部と、Kyrie、Sequentia(続誦)のLacrimosa(涙の日よ)8小節目までおよびOffertorium(奉献誦)の主要部の草稿である。それ以外の部分は彼の弟子であり、完成にあたっての指示を口頭で受けていたジュスマイヤーが主に補作を手がけた。だが、いくつかの個所で音楽理論上の誤りや欠格が見られる点で彼は批判され続けた。
昨今では彼になり代わり、新しい補作を試みる研究家に事欠かない。しかし、死にゆくモーツァルトの傍にいた作曲家であって、全力を傾けて慎重に再現したという功績と優位に勝てる者は、現代には存在しないのである。
楽器編成にも配慮がなされている。フルート、オーボエ、クラリネットといった古色の華やかな楽器を使わないかわりに、バセットホルン(クラリネットより低音部を扱う楽器)またはホルンとファゴットを基調とする。それに弦楽が加わった深い厳粛な雰囲気の中で、レクイエムは始まる。モーツァルトが唯一純粋に完成させたIntroitusが、忘れられない印象を残して2重フーガのKyrieに入る。Sequentiaは6部に分かれ、それぞれがテクストの内容に従って音楽が形成されていくが、中でも絶筆とされているLacrimosaは、モーツァルト自身の死の哀愁が漂う、悲劇的な美しさが心を打つ。Offertoriumの2つの部分は、雄大な讃歌と安らかな祈りの歌が、共通に表れる力強いフーガによって結ばれる。以後はジュスマイヤーによる創作であるが、モーツァルトの旋律を活用することによって、彼の音楽の忠実な再現を目指している。最後はIntroitusとKyrieの古楽をそのまま転用して、全曲の統一が果たされている。
![]()